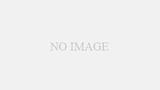🌀 導入
東京湾サワラキャスティングでは、ブレードジグを沈めて巻いて食わせる釣りが主流。
でも、PEラインの太さやブレードの有無によって、沈み方は大きく変わる。
計算上、どのくらい違うのか、AI(五十六)と導き出してみた。
⏱ 沈下速度の比較(Time to Bottom)
以下の条件で、沈下を計算。
- 水深:20m
- ジグ:50g
- ライン:PE1.2/1.5/2.0号
- ブレード:あり/なし
- 計測時間:30秒
結果はこちら👇
✅ 細いPEほど早く沈み、底に長く滞在する。
※ブレードの形状(コロラド/ウィロー)によっても沈下速度は異なる。
今回の数値は、一般的なブレード付きジグ(平均的な抵抗)を想定したもの。
🌀 弧の違い(Arc Shape)
太いラインほど水の抵抗を受けて大きな弧を描く。一方、細いラインは抵抗が少なく、ほぼ直線的に沈む。
下の図は、PE号数ごとの沈下軌道(Arc Shape)を可視化したもの。
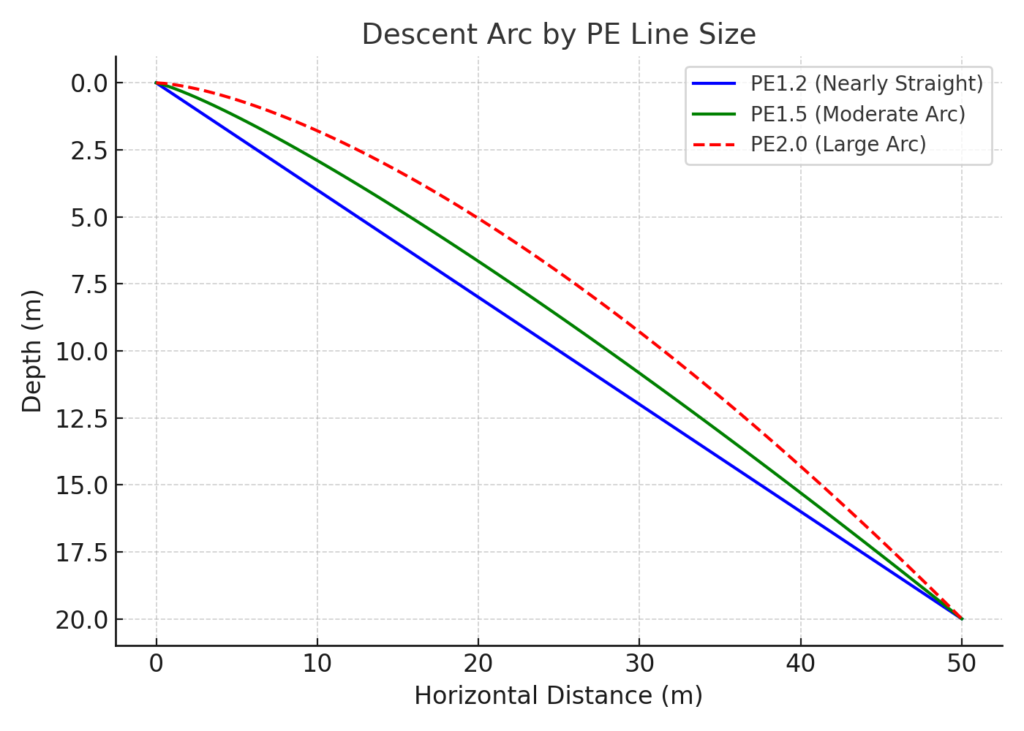
細糸は弧が小さく、狙いのレンジに早く入る。逆に、太糸は弧が大きく、レンジ到達が遅くなる。
🧾 まとめ
- 細糸:早く沈む/弧が小さい/チャンスが長い
- 太糸:沈みにくい/弧が大きい/チャンスが短い
風や潮流などの要素も加わるが、ライン選びの目安として知っておくと有利かと思う。
✅ 結論
「沈下速度」と「弧の大きさ」は、PE号数で決まる。
次回予告:「なぜ沈まないのか?ブレードの抗力と揚力」
キラキラと回転するブレード。「アピール力」の反面、“沈まない”原因にもなっている。
ブレードが生むのは「抗力」と「揚力」。
水流を受けて、ジグ全体に浮き上がる力が働く。その結果、沈下速度は遅くなり、底レンジの滞在時間は短くなる。
次回は、この「ブレードの抵抗」を数値でシミュレーション。
🌀コロラド vs ウィロー、どちらが沈みにくい?
📈 回転数や面積の違いが、どれほど沈下に影響するのか?
“見せる”と“沈める”のバランスを、物理的に検証してみようと思う。